REITの税金は、株式投資信託とほとんど同じです。ただ、"REITの税金"と、"株式投資信託の税金"とでは、若干違う点もありますので、ここでは"REITの税金"にしぼって解説します。では、REITの税金はどうなっているのでしょうか?
REITの税金は、株式投資信託と同じく、譲渡益と、分配金とで税金の扱いが異なります。
REITの譲渡益は、"申告分離課税"になる
REITの譲渡益は、申告分離課税になります。申告分離課税とは、一定の所得を、他の所得と"分けて"計算する課税方式です。他の所得と分けて計算する―「一定の所得」には、REITの譲渡益・分配金も含まれます。「一定の所得」であるREITの譲渡益は、他の「一定の所得」である―"上場株式(ETF含む)・株式投資信託等の譲渡損失"と損益通算できます。
図:REITの譲渡益と、株式投資信託等の譲渡損失と―の損益通算
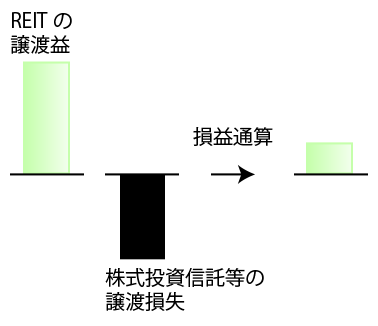
REITの譲渡益は申告分離課税なので、一律の税金がかかります。一律の税金の"一律"とは、20.315%です。20.315%の税金の内訳は、所得税:15.315%・住民税:5%です。なお、所得税の15.315%は、本来の税率:15%に、復興特別所得税:0.315%(=15%:所得税×2.1%)が加算されています(平成49年まで)。
REITの分配金は、"申告分離課税"と"総合課税"との中からいずれかを選択する
REITの分配金は、投資家が"申告分離課税"と"総合課税"とのいずれかを選択します。申告分離課税を選ぶと、株式投資信託などで発生した"譲渡損失"と損益通算できます。総合課税を選ぶと、配当控除が利用できるようになります。ただし、REITの分配金は配当控除の対象ではないため、配当控除は利用できません。
REITで発生した分配金は、"申告分離課税"と"総合課税"とのいずれかを―投資家が選択できます。<申告分離課税>とは、他の所得と"分けて"、税金を計算する課税方式です。また、<総合課税>とは、他の所得と"合算して"、税金を計算する課税方式です。
<申告分離課税>を選択した分配金は、「上場株式(ETF含む)や、株式投資信託等の―"譲渡損失"」と損益通算できます。なお、損益通算できるのは、<申告分離課税>を選択したときだけで、<総合課税>を選択した場合は、損益通算できません。
図:REITの分配金と、株式投資信託等の譲渡損失と―の損益通算
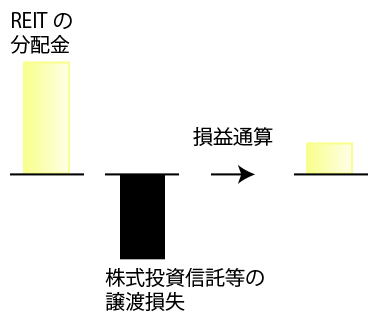
申告分離課税を選択した場合、一律20.315%の税金がかかります。20.315%の税金の内訳は、所得税:15.315%(復興特別所得税含む)・住民税:5%です。
<総合課税>を選択した分配金は、配当控除が使えます。配当控除とは、一定の条件を満たす―"分配金"や"配当"にかかる税金を少なくできる制度です。ただし、REITの分配金は、「一定の条件を満たす分配金"ではない"」ので、<総合課税>を選択しても配当控除は使えません。
総合課税を選択した場合、課税所得額(=総所得から各種控除分を控除したあとの金額)に応じた税率の―税金がかかります。"課税所得額に応じた税率"とは、15%~50%(+復興特別所得税)です。15%~50%の税金の内訳は、所得税:5%~40%(+復興特別所得税:所得税×2.1%)・住民税:10%です。上記からわかるように、所得税のみ、税率が5%~40%に変化します。たとえば、課税所得額が300万円だった場合の税金は、
- 所得税:202,500円(=3,000,000円×10%-97,500円 ※下の"所得税の速算表"を参照)。
- 復興特別所得税:4,252円(=202,500円×2.1% ※端数切り捨て)。
- 住民税:300,000円(=3,000,000円×10%)。
となります。
図:所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0 円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500 円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500 円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000 円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000 円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000 円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000 円 |
上記の表は、 No.2260 所得税の税率[国税庁](外部サイト)より引用。