長期投資をする場合、リスク許容度の計算に必要な―最大損失率*の数値が変わってしまう点に注意が必要です。長期投資による―最大損失率の変化の例として、"リターン:5%・リスク15%の資産を5年運用した場合"を考えてみましょう(簡便さのためここでは信託報酬は0%とします)。まず、"リターン:5%を5年間運用したとき"の期待リターンは、28%(=(1+5%)^5年-1)です。次に、"リスク:15%を5年運用したとき"の想定リスクは、34%(=15%×√5年)です。上記の数値を元に最大損失率を計算すると、最大損失率が、-40%(=28%-34%×2)になります。1年間の運用であれば-25%(=5%-15%×2)であったのと比較すると、最大損失率が大きくなったことがわかります。では、このような"最大損失率の増加"が気になる方は、長期投資時のリスク許容度をどう調整すればよいのでしょうか?
* 最大損失率の計算式は、"リターン-信託報酬-(リスク×2)"です。
以下のように、よりリスクの低い資産組みあわせに変更すると良いでしょう。
なお、"リスク許容度:10%の資産組みあわせで運用されている方"と、"リスク許容度:50%以上の方"とは、最大損失額の増加を気にする必要はありません。 "リスク許容度:10%の資産の組みあわせ"(=国内債券:70%・国内株式:15%・外国株式:15%)は、運用年数が多くなっても最大損失額が-13.10%までしか上がらないからです。 また、"リスク許容度:30%の資産の組みあわせ"(=国内株式:50%・外国株式:50%)は、運用年数が多くなっても最大損失率が-53.06%までしか上がらないからです。
リスク許容度:30%→20%に、資産組みあわせを変更
リスク許容度:30%の資産の組みあわせ(=国内株式:50%・外国株式:50%、信託報酬:0.5%)は、長期投資すると-53.06%まで最大損失率が上がってしまいます。-53.06%の最大損失率になるのは、運用から8年目です。最大損失率の変化の流れは以下です。
- 最大損失率は、運用開始から徐々に上がり、8年目にもっとも高くなります(-53.06%)。
- 最大損失率は、8年を過ぎると徐々に下がって行き、22年目には最大損失時でも元本割れをしなくなります(あくまで計算上です)。
図:リスク許容度:30%の資産組みあわせの―最大損失率の変化
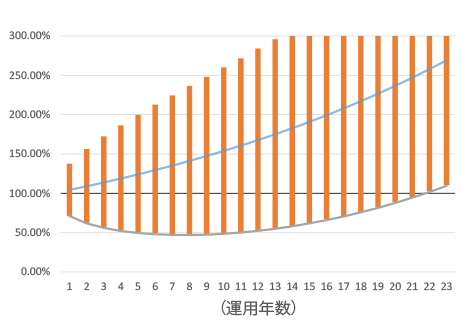
![]()
- 青い線が、リターンの伸びを表しています。リターンは累積で伸びていきます。
- オレンジの棒が、リスクの伸びを表しています。リスクは√倍で伸びていきます。リターンは、オレンジ色の範囲(=リスクの範囲)のどれかに収まることになります。
- 灰色の線が、最大損失率の変化を表しています。最大損失率は、いったん落ち込んだ後、徐々に上向きになっています。22年目には最大損失の場合でも100%を超えています(=最大損失の場合でも元本割れはしない)。
一方、リスク許容度:20%の資産の組みあわせ(=国内債券:30%・国内株式:35%・外国株式:35%、信託報酬:0.5%)は、長期投資をしても-32.95%までしか最大損失率が上がりません。-32.95%の最大損失率になるのは、運用から6年目です。最大損失率の変化の流れは以下です。
- 最大損失率は、運用開始から徐々に上がり、6年目にもっとも高くなります(-32.95%)。
- 最大損失率は、6年を過ぎると徐々に下がって行き、19年目には最大損失時でも元本割れをしなくなります。
図:リスク許容度:20%の資産組みあわせの―最大損失率の変化
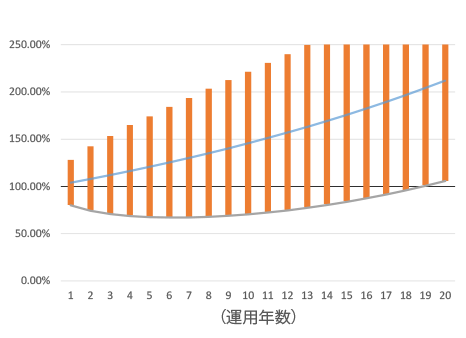
そのため、どうしても「長期投資による最大損失率の変化」が気になる場合、リスク許容度:30%の方は、リスク許容度:20%の資産組みあわせに変えても良いかもしれません。リスク許容度:20%の資産組みあわせに変えることで、長期投資によってリスクが増加しても、最大損失率が-32.95%までしか上がらなくなるからです。
リスク許容度:20%→15%に、資産組みあわせを変更
リスク許容度:20%の資産の組みあわせ(=国内債券:30%・国内株式:35%・外国株式:35%、信託報酬:0.5%)は、長期投資すると-32.95%まで最大損失率が上がってしまいます。-32.95%の最大損失率になるのは、運用から6年目です。最大損失率の変化の流れは以下です。
- 最大損失率は、運用開始から徐々に上がり、6年目にもっとも高くなります(-32.95%)。
- 最大損失率は、6年を過ぎると徐々に下がって行き、19年目には最大損失時でも元本割れをしなくなります。
図:リスク許容度:20%の資産組みあわせの―最大損失率の変化
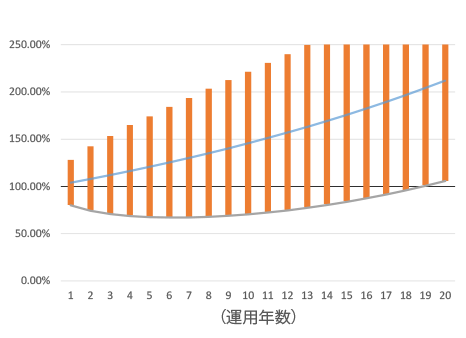
一方、リスク許容度:15%の資産の組みあわせ(=国内債券:50%・国内株式:25%・外国株式:25%、信託報酬:0.5%)は、長期投資をしても-21.54%までしか最大損失率が上がりません。-21.54%の最大損失率になるのは、運用から5年目です。最大損失率の変化の流れは以下です。
- 最大損失率は、運用開始から徐々に上がり、5年目にもっとも高くなります(-21.54%)。
- 最大損失率は、5年を過ぎると徐々に下がって行き、16年目には最大損失時でも元本割れをしなくなります。
図:リスク許容度:15%の資産組みあわせの―最大損失率の変化
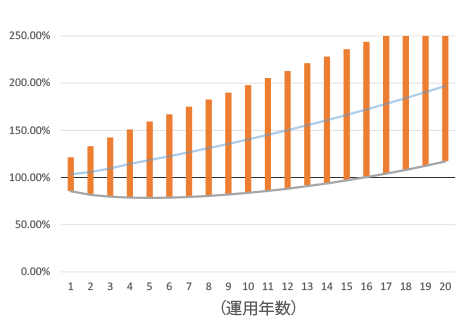
そのため、どうしても「長期投資による最大損失率の変化」が気になる場合、リスク許容度:20%の方は、リスク許容度:15%の資産組みあわせに変えても良いかもしれません。リスク許容度:15%の資産組みあわせに変えることで、長期投資によってリスクが増加しても、最大損失率が-21.54%までしか上がらなくなるからです。