投資信託にはさまざまなコストがかかります。投資信託のコストは、以下です。まず、投資信託のコストには、投資信託を購入する際にかかる―販売手数料があります。次に、投資信託のコストには、投資信託を売却する際にかかる―信託財産留保額があります。そして、投資信託のコストには、投資信託を保有している間ずっとかかる―信託報酬があります。なお、これらの中の"販売手数料"・"信託財産留保額"は、かからないファンドもあります。
これらの投資信託のコストの中で、投資信託を保有している間ずっとかかる―信託報酬が一番重要です。信託報酬が一番重要な理由は、長期保有しても、コストの負担を軽くすることができないからです。具体的には、以下です。(1)まず、販売手数料・信託財産留保額などの―「販売時、もしくは売却時に一度だけかかるコスト」は、投資信託を長期で保有すれば"1年あたりのコストの負担"を軽くすることができます*が、(2)信託報酬のように「保有している間ずっとかかるコスト」は、投資信託を長期間で保有しても"1年あたりのコストの負担"を軽くすることができない―からです。
![]()
ただ、投資信託の保有中にかかるコストは、信託報酬だけではありません。投資信託を保有している際にかかる―信託報酬以外のコストとは、"売買委託手数料"・"有価証券取引税"・"保管費用等"です。
これらの"信託報酬以外の手数料を含めた―実際にかかるコスト(=実質コスト)" は、目論見書に記載されていないので注意が必要です。実質コストが記載されない理由は、信託報酬以外のコストは、毎年、数値が一定ではないからです。
しかし、投資信託の実質コストは、目論見書と、運用報告書との数値から計算することができます。では、投資信託の実質コストは、どうやって計算すればいいのでしょうか?
以下の手順でおこないます。なお、以下の計算例では、外国株式インデックスeの実質コストを計算しています。
1.計算に必要な数値を取得する
1-1.計算したい投資信託の―目論見書から、信託報酬率を取得する。
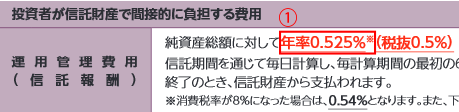
※ 画像は、外国株式インデックスeの交付目論見書 6ページから引用
1-2.計算したい投資信託の―運用報告書から、"信託報酬額"の数値を取得する。
1-3.計算したい投資信託の―運用報告書から、" 合計コスト"の数値を取得する。
なお、合計コストとは、「合計」に記載されている数値で、(a)信託報酬・(b)売買委託手数料・(c)有価証券取引税・(d)保管費用等 を合計した数値(="信託報酬"と、"保有中にかかる信託報酬以外のコスト"とを含めたコスト)です。
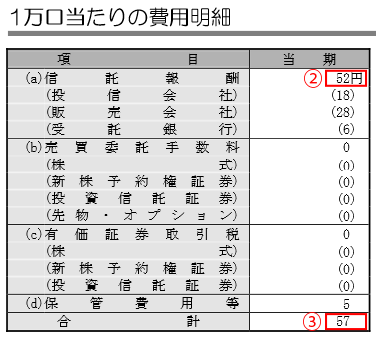
※ 画像は、外国株式インデックスeの運用報告書 5ページから引用
2.1.の数値を使って、平均基準価額を計算する
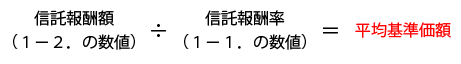
例: 52円 ÷ 0.525% = 9904.7619円
![]()
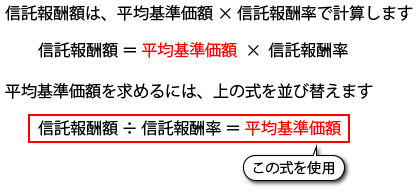
3.1.2.の数値を使って、実質コストを計算する
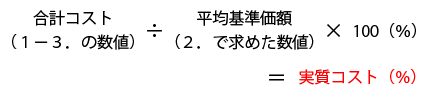
例: 57円 ÷ 9904.7619円 × 100(%) = 0.57548077%
![]()
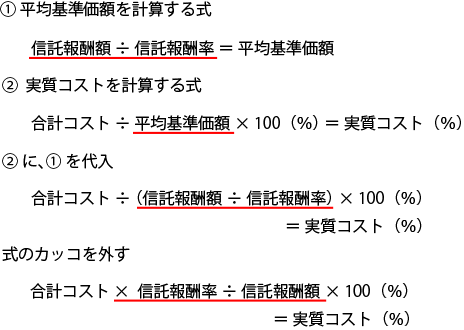
例: 57円 × 0.525% ÷ 52円 × 100(%) = 0.57548077%